毎月の給与明細を見て「税金が高いな」とため息をついていませんか。実は、サラリーマンでも正しい知識を身につければ、合法的に税金の負担を軽くできます。この記事では、初心者でも簡単に始められる節税対策を網羅的に解説します。年末調整でできる手軽な方法から、確定申告でさらに手取りを増やす方法、そして資産形成も同時にできるお得な制度まで、あなたに合った節税術がきっと見つかります。
サラリーマンが納める税金の基本をおさらい

毎月の給料からは、主に「所得税」と「住民税」という2つの税金が天引きされています。これらの税額は、年収からさまざまな「控除」を差し引いた後の「課税所得」を基に計算されます。つまり、この控除額を大きくすることが、節税の基本的な仕組みです。控除には、所得から差し引く「所得控除」と、計算された税額から直接差し引く「税額控除」があります。まずはこの仕組みを理解することが、手取りを増やすための第一歩といえるでしょう。
【初心者向け】まずはコレだけ!年末調整でできる節税対策

「節税は難しそう」と感じる方もご安心ください。多くのサラリーマンにとって最も身近な節税のチャンスが、年末に行う「年末調整」です。会社に指定された書類を提出するだけで、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があります。ここでは、比較的簡単に手続きが完了する、年末調整で適用できる代表的な所得控除を紹介します。まずはこれらの制度を活用し、確実に手取りアップを目指しましょう。
生命保険料控除で保険料負担を軽減
生命保険や個人年金、介護医療保険に加入しているなら、ぜひ活用したいのが生命保険料控除です。この制度は、年間に支払った保険料の一部を所得から差し引けるというものです。対象となるのは「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3種類。新制度では、それぞれ最大4万円、合計で最大12万円の所得控除が受けられます。手続きは、秋ごろに保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」を年末調整の書類に添付するだけなので、忘れずに行いましょう。
地震保険料控除で万が一の備えもお得に
もしもの災害に備えて地震保険に加入している場合、その保険料も所得控除の対象になります。地震保険料控除は、年間に支払った地震保険料の金額に応じて、最大で5万円まで所得から差し引ける制度です。火災保険とセットで契約している場合でも、地震保険料の部分だけが対象となるので注意しましょう。こちらも生命保険料控除と同様に、保険会社から送付される控除証明書を年末調整で提出するだけで手続きは完了です。万が一への備えが、節税にもつながるお得な制度といえます。
扶養控除・配偶者控除の対象を確認しよう
ご家族を養っている方は、扶養控除や配偶者控除が適用できるか必ず確認しましょう。これらの控除は、納税者本人とご家族の所得状況によって適用条件や控除額が異なります。2025年以降の主な基準は以下の通りです。
配偶者控除と配偶者特別控除
納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が一定額以下の場合に適用されます。
- 配偶者控除
配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)の場合に適用。- 納税者本人の合計所得900万円以下:控除額38万円
- 納税者本人の所得が900万円以上:控除額が段階的に減少し、1,000万円超で控除の適用対象外となります。
- 配偶者特別控除
配偶者の合計所得が58万円超133万円以下(給与収入のみなら123万円超201万6,000円未満)の場合に、所得に応じて段階的に控除されます。- 最大控除額:38万円(配偶者の合計所得95万円以下の場合)
- 控除対象外:配偶者の年間給与収入が201万6,000円を超えると対象外
扶養控除
扶養親族の年齢によって控除額が変わります。
| 扶養親族の区分 | 年齢 | 控除額 |
| 一般の控除対象扶養親族 | 16歳以上 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 同居老親等:58万円 同居老親等以外:48万円 |
【実践編】確定申告でさらに手取りを増やす節税対策

年末調整だけでは適用できない、より節税効果の高い制度もたくさんあります。それらを活用するには「確定申告」という手続きが必要です。「手間がかかりそう」と思うかもしれませんが、近年はスマートフォンからでも手軽に申告できるシステムが整っています。少しの手間をかけるだけで、手取り額に大きな差が生まれることもあります。ここでは、確定申告でできる代表的な節税対策を見ていきましょう。
ふるさと納税(寄附金控除)で返礼品も楽しむ
ふるさと納税は、自分が応援したい自治体を選んで寄付ができる制度です。寄付した金額のうち、2,000円を超える部分が所得税や住民税から控除されます。厳密には税金を前払いする仕組みですが、寄付の見返りとしてお肉や果物といった地域の特産品などを受け取れるため、実質的な自己負担は2,000円で済む、非常にお得な制度です。控除上限額は年収や家族構成で変わるため、事前にシミュレーションサイトで確認してから始めましょう。
医療費控除・セルフメディケーション税制を賢く活用
年間の医療費が多くかかった年は、医療費控除を受けられる可能性があります。これは、1年間の医療費が10万円(総所得200万円未満の場合は所得の5%)を超えた場合に、その超過分を所得から控除できる制度です。ご自身の医療費だけでなく、生計を一つにする家族の分も合算できます。また、特定の市販薬を年間12,000円以上購入した場合は、セルフメディケーション税制という制度も選択可能です。どちらか一方しか利用できないため、より控除額が大きい方を選びましょう。
住宅ローン控除(初年度)でマイホームの負担を軽く
住宅ローンを利用してマイホームを購入またはリフォームした場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が利用できます。この制度は、年末時点でのローン残高の一定割合が、所得税から直接差し引かれる「税額控除」です。そのため、非常に大きな節税効果が期待できます。適用を受ける初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。
住宅ローン控除で控除される金額は、年末の住宅ローン残高に控除率0.7%を掛けた額が基本となり、それに加えて住宅の種類や入居年によって設定されている借入限度額や納税額(所得税と住民税)によって決まります。
控除額の計算方法
住宅ローン控除額は、以下の3つの金額を比較して、最も小さい額が適用されます。
- 年末の住宅ローン残高 × 0.7%
- 住宅の種類ごとの年間最大控除額(借入限度額の0.7%)
- その年に支払った所得税額と、控除しきれない場合の住民税からの控除上限額(最大9万7,500円または13万6,500円)
住宅の種類ごとの最大控除額(2024年入居の場合)
2024年以降に入居する場合、住宅の省エネ性能に応じて借入限度額と控除期間が設定されています。
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 控除期間 | 年間最大控除額 (借入限度額×0.7%) |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 13年間 | 35万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 13年間 | 31.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 13年間 | 21万円 |
| その他の新築・買取再販 | ※原則対象外 | ※原則対象外 | ※原則対象外 |
| 中古住宅 | 2,000万円 | 10年間 | 14万円 |
※2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準を満たしている必要があります。その他の住宅は原則として控除の対象外です。
控除額のシミュレーション例
年末のローン残高が3,000万円で、省エネ基準適合住宅(最大控除額21万円)に入居した場合を想定します。
- 計算額: 3,000万円 × 0.7% = 21万円
- 所得税額: 15万円
- 住民税控除上限額: 9万7,500円(または13万6,500円)
この場合、まず所得税15万円が控除されます。残りの控除可能額6万円(21万円-15万円)が、翌年の住民税から上限額の範囲内で控除されます。
控除額は納税額やローン残高によって変わるため、正確な金額を知るには、金融機関や税務署のシミュレーションを利用すると良いでしょう。
【資産形成も】将来を見据えた攻めの節税対策

ここまでは、支払う税金を減らす「守りの節税」を紹介してきました。しかし、中には将来のための資産を増やしながら、同時に税金の負担も軽くできる「攻めの節税」ともいえる方法があります。税制優遇制度を上手に活用することで、効率的に資産形成を進めることが可能です。ここでは、特に人気の高い2つの制度について解説します。
iDeCo(個人型確定拠出年金)で老後資金を準備
iDeCo(イデコ)は、ご自身で掛金を拠出し、好きな金融商品で運用しながら老後資金を準備する私的年金制度です。最大の魅力は、その強力な税制優遇にあります。まず、毎月の掛金が全額所得控除の対象になるため、所得税と住民税が軽減されます。さらに、運用で得られた利益(運用益)も非課税となり、将来年金として受け取る際にも税金の優遇が受けられます。ただし、原則として60歳まで資金を引き出せないため、長期的な視点で取り組むことが重要です。
新NISA(少額投資非課税制度)で運用益を非課税に
新NISAは、個人の資産形成を後押しするための税制優遇制度です。通常、株式や投資信託などで得た利益(運用益)には約20%の税金がかかりますが、NISA口座内で得た利益には税金がかかりません。iDeCoのような掛金の所得控除はありませんが、いつでも自由に資金を引き出せるのが大きなメリットです。2024年から制度が新しくなり、非課税で投資できる上限額も拡大しました。節税と同時に、柔軟な資産運用を始めたい方におすすめの制度です。
副業をしているサラリーマン向けの節税対策
最近では、副業で収入を得るサラリーマンも増えています。副業で得た所得が年間20万円を超えた場合は、原則として確定申告が必要です。このとき、節税の鍵を握るのが「経費」の計上です。副業のために購入したパソコンの費用や、打ち合わせの交通費、学習のための書籍代などは経費として認められる可能性があります。収入からこれらの経費を差し引くことで課税所得を圧縮し、節税につなげられます。日頃から領収書を保管しておく習慣をつけましょう。
サラリーマンが節税対策を行う際の注意点

節税に取り組む際には、いくつか注意すべき点があります。まず、節税を意識するあまり、不要な保険に加入したり、無駄な買い物をしたりと、本末転倒な支出を増やさないように気をつけましょう。また、確定申告が必要な場合は、必ず期限内(原則として翌年の3月15日まで)に手続きを済ませることが重要です。期限を過ぎると、ペナルティが課される場合があります。そして最も大切なのは、脱税と節税は全く違うということです。必ずルールに則った正しい方法で、賢く税金対策を行いましょう。
まとめ
この記事では、サラリーマンが取り組めるさまざまな節税対策を紹介しました。年末調整で手軽にできるものから、確定申告が必要なもの、さらには資産形成と両立できるものまで、ご自身の状況に合わせて選ぶことができます。まずは自分にできそうな方法を一つでも見つけて、実際に行動に移すことが手取りを増やすための大切な第一歩です。賢く税金と付き合い、計画的な資産形成でより豊かな未来を築いていきましょう。
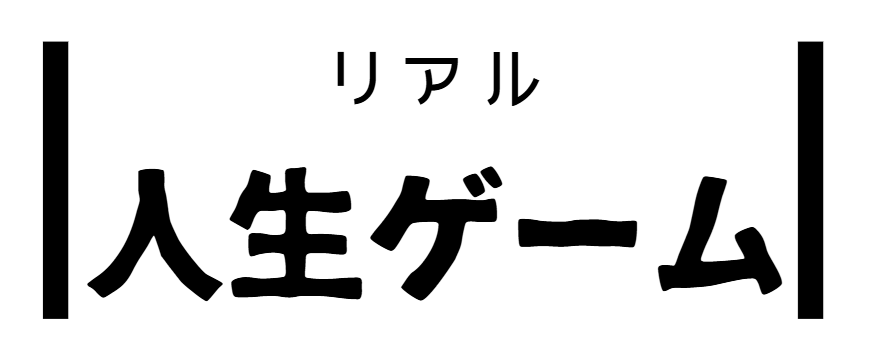


コメント