「給与明細を見て、手取り額が思ったより少なくて驚いた」。多くのサラリーマン、特に新社会人の方がそう感じるのではないでしょうか。この記事を読めば、給与から天引きされる税金と社会保険料の基本がわかります。会社員が納めるお金の仕組みを理解し、将来の資産形成に役立てていきましょう。
給与から天引きされるのは大きく分けて2種類「税金」と「社会保険料」
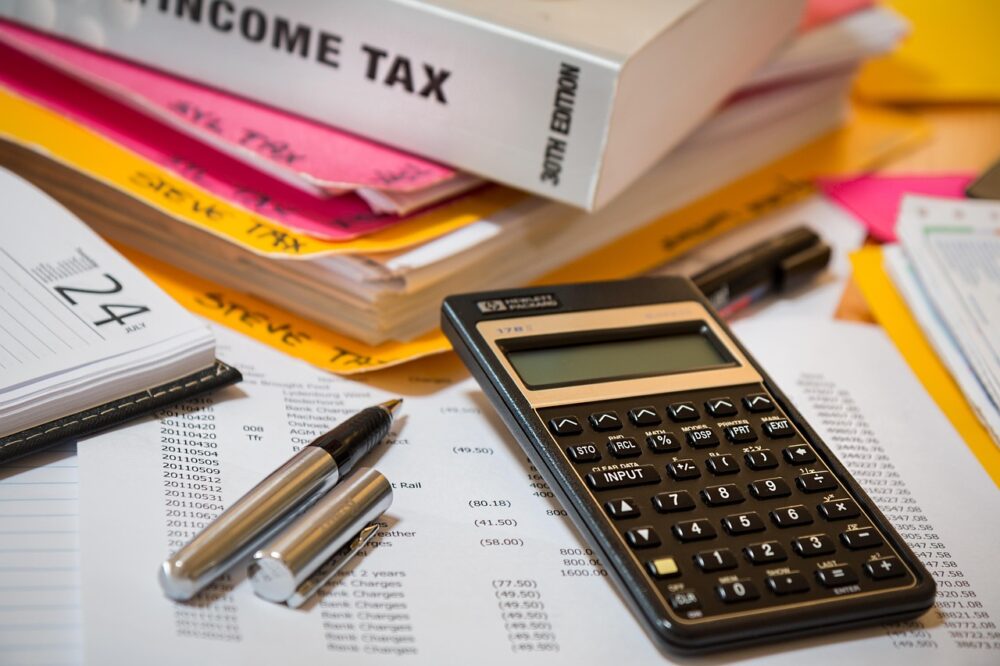
給与明細は、大きく「支給」「控除」「勤怠」の3つの項目で構成されています。この中で、手取り額に直接関係するのが「支給」と「控除」です。
「支給」は基本給や残業代、各種手当を合計した、いわゆる「額面」の給与を指します。そして「控除」は、その支給額から差し引かれるお金のことです。
この控除されるものには、大きく分けて**「税金」と「社会保険料」**の2種類があります。これらは、社会を支えたり、万が一の事態に備えたりするために、すべての会社員が支払う義務のある大切なお金です。
実際に銀行口座に振り込まれる「手取り額」は、総支給額から税金と社会保険料を差し引いた金額になります。
給与から引かれる税金は「所得税」と「住民税」

サラリーマンの給与から天引きされる税金は、主に「所得税」と「住民税」の2つです。これらは私たちが社会の一員として、国や地域を支えるために納めるお金です。それぞれ納める先や計算方法が異なるため、基本的な違いをしっかり押えておきましょう。
所得税|個人の所得に対してかかる国の税金
所得税は、個人の1年間の所得に対してかかる国の税金です。所得とは、給与やボーナスなどの収入から、特定の経費などを差し引いた儲けの部分を指します。
所得税の大きな特徴は**「累進課税(るいしんかぜい)」**という仕組みです。これは、所得が多い人ほど高い税率が適用される仕組みをいいます。
会社員の場合、会社が毎月の給与から概算の所得税額を天引きして、本人に代わって国に納めています。これを**「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」**といいます。そして年末に「年末調整」を行い、1年間の正しい税額を計算し、過不足を精算する流れになっています。
住民税|住んでいる自治体に納める地方の税金
住民税は、住んでいる都道府県や市区町村に納める地方の税金です。教育、福祉、ごみ処理、消防など、私たちの身近な行政サービスを維持するために使われます。
所得税との大きな違いは、前年の所得をもとに税額が計算される点です。そのため、新社会人の場合、住民税の天引きが始まるのは入社2年目の6月からになります。「2年目になったら手取りが減った」と感じるのは、この住民税の支払いが始まるのが主な理由です。
税率は所得に関わらず、原則として一律約10%です。所得税と同じく、会社が毎月の給与から天引きして自治体に納めてくれます。
給与から引かれる社会保険料は主に3種類

税金と並んで給与から天引きされるのが、社会保険料です。これは、病気やケガ、失業といった万が一の事態に備えるための「保険」の役割を果たします。
社会保険料は、会社と従業員が保険料を半分ずつ負担する**「労使折半(ろうしせっぱん)」**が基本です。つまり、給与明細に記載されている社会保険料と同額を会社も負担してくれています。そのため、全額を自分で負担するよりも少ない金額で手厚い保障を受けられるのが大きな特徴です。
健康保険料|病気やケガの医療費に備える
健康保険料は、病気やケガで病院にかかった時の医療費負担を軽くするための保険料です。
私たちが病院の窓口で支払う医療費が原則3割で済むのは、この健康保険制度のおかげです。また、高額な医療費がかかった場合に一部が払い戻される制度や、病気で会社を休んだ際に給与の一部が支給される「傷病手当金」といった保障も受けられます。保険料は給与額に応じて決まり、加入している健康保険組合などによって保険料率が異なります。
厚生年金保険料|将来の年金に備える
厚生年金保険料は、将来、原則65歳から「老齢年金」を受け取るために積み立てる保険料です。
これは、すべての国民が加入する国民年金に上乗せされる「2階建て」の部分にあたります。将来受け取る年金額は、納めた保険料が多いほど増える仕組みです。また、老後のためだけでなく、自身が障害を負った場合の「障害年金」や、死亡した場合に遺族が受け取れる「遺族年金」といった、万が一の時の保障も含まれています。
雇用保険料|失業した時などの生活に備える
雇用保険料は、会社を退職して失業状態になった際に、生活を支える「失業手当」などを受け取るための保険料です。
失業手当だけでなく、育児や介護で会社を休む際の給付金や、スキルアップを目指して専門学校などに通う際の費用を一部補助してくれる「教育訓練給付金」といった制度もあります。働く人が安心してキャリアを継続したり、再就職を目指したりするためのセーフティーネット(安全網)の役割を担っています。
「税金」と「社会保険料」は何が違う?

給与から同じように天引きされる税金と社会保険料ですが、その目的や使い道は大きく異なります。
税金は、国や自治体が道路や学校の整備、警察や消防といった公共サービスをすべての人に提供するために使われます。使い道は幅広く、直接的な見返りを個人が受けるわけではありません。
一方、社会保険料は、加入者自身やその家族が病気や老後、失業といったリスクに直面した際に、給付という形で直接的な見返りを受けるための「保険料」です。目的が明確で、支払った保険料が将来の自分を守ることにつながります。
手取り額の計算方法をわかりやすく解説
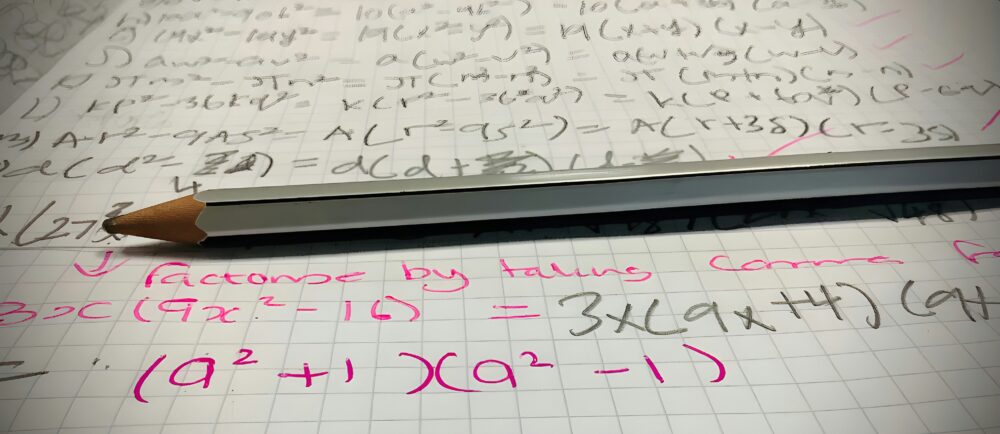
これまでの内容を踏まえると、手取り額がどのように決まるのかが見えてきます。計算方法はいたってシンプルです。
【手取り額 = 総支給額 ー (税金 + 社会保険料)】
一般的に、手取り額は総支給額の**約75%~85%**になるといわれています。たとえば、総支給額が25万円の場合、手取り額は18万7,500円から21万2,500円程度が目安です。扶養家族の有無や年齢によっても変動しますが、この割合を覚えておくと自分の給与がおおよそどうなるか把握しやすくなります。この仕組みがわかれば、額面と手取りの差にも納得できるはずです。
40歳になると「介護保険料」も引かれる

将来的に控除額に変化が訪れるタイミングがあります。それが40歳です。
日本では、将来介護が必要になった時に少ない自己負担で介護サービスを利用できる「介護保険制度」があります。この制度の保険料は、40歳になると支払う義務が生じます。
会社員の場合、40歳になった月から、健康保険料とあわせて介護保険料が給与から天引きされるようになります。そのため、同じ給与額でも40歳になると手取りが少し減ることになります。将来の家計を考えるうえで、覚えておきたいポイントの一つです。
まとめ
給与から天引きされるのは、「所得税」「住民税」という税金と、健康保険料などの各種社会保険料です。これらは社会の仕組みを支え、万が一の時に自分や家族を守るために欠かせない大切なお金といえます。
まずはご自身の給与明細を改めて確認し、何にいくら支払っているのか、お金の流れを把握することから始めてみてください。税金や社会保険料の正しい知識は、将来の安心な暮らしと、賢い資産形成への確かな第一歩になるはずです。
給与から天引きされるようになります。そのため、同じ給与額でも40歳になると手取りが少し減ることになります。将来の家計を考えるうえで、覚えておきたいポイントの一つです。
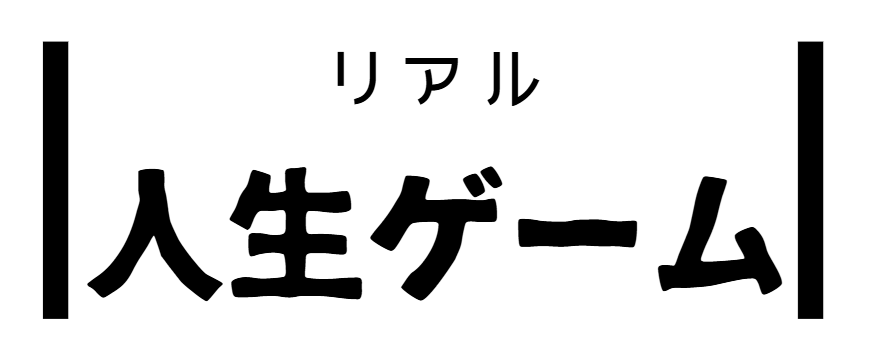


コメント