「投資で資産を増やしたいけど、計算が苦手…」と感じていませんか。この記事を読めば、誰でも簡単に資産が増える期間がわかる投資の法則が身につきます。まずは投資の法則を知るメリットから、具体的な計算方法までわかりやすく解説します。
投資の法則を知る3つのメリット
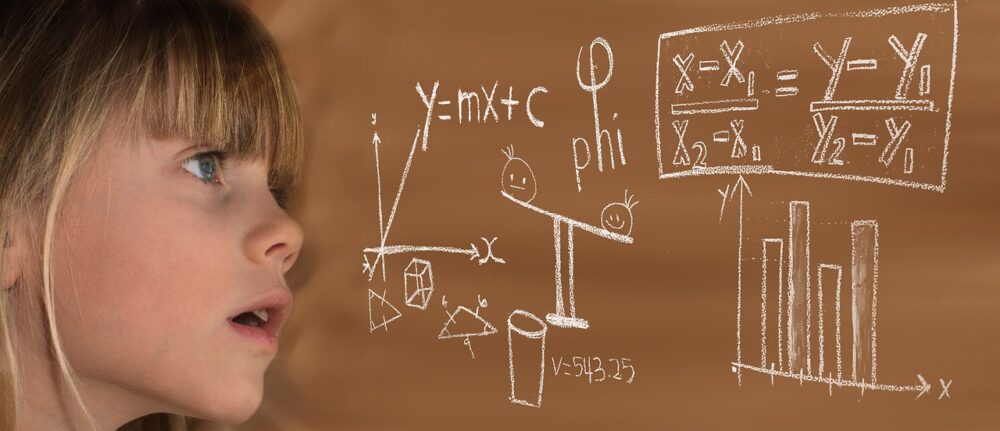
投資の法則を学ぶことには、大きく分けて3つのメリットがあります。まず1つ目は、資産形成の目標設定が具体的になることです。いつまでに資産を2倍にしたいか、そのためには年利何%で運用すればよいかが明確になります。
2つ目は、複利の効果を実感しやすくなることです。複利とは、利益を元本に加えて再投資することで、雪だるま式に資産が増える効果のことです。法則を使えば、その強力なパワーを数字で理解でき、長期投資へのモチベーションが上がります。
そして3つ目は、冷静な投資判断の助けになることです。市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点を持つための指針となります。これらの法則は、あなたの資産形成における強力な羅針盤になるでしょう。
資産が2倍になる期間がわかる 72の法則

数ある投資の法則のなかで、最も有名で便利なのが「72の法則」です。これは「お金が2倍になるまでのおおよその期間」を簡単に計算できる法則です。このシンプルな計算式を知っているだけで、あなたの資産運用の見通しがぐっと立てやすくなります。これから、その具体的な計算方法とシミュレーションを見ていきましょう。
72の法則の具体的な計算方法
72の法則の計算方法は非常にシンプルです。以下の式に当てはめるだけです。
72 ÷ 金利(%) ≒ 資産が2倍になる年数
例えば、100万円を年利5%で運用できた場合を考えてみましょう。「72 ÷ 5」で、答えは約14.4年となります。つまり、約14年半で100万円が200万円になるという目安がわかります。
逆に、期間から必要な金利を求めることも可能です。
72 ÷ 年数 ≒ 必要な金利(%)
もし10年で資産を2倍にしたいなら、「72 ÷ 10」で7.2%の金利が必要だとわかります。このように、目標達成のための具体的な数値目標を立てるのに役立ちます。
【年利別】72の法則シミュレーション
金利の違いが、資産が2倍になるまでの期間にどれほど影響するか見てみましょう。仮に100万円を運用した場合、200万円になるまでの期間は以下のようになります。
| 年利 | 資産が2倍になる期間 |
| 1% | 約72年 |
| 3% | 約24年 |
| 5% | 約14.4年 |
| 7% | 約10.3年 |
このように、わずか数%の金利差が、長い年月で見ると非常に大きな差を生むことがわかります。複利の効果を最大限に活かすには、少しでも高い利回りを目指すことが大切です。あなたの目標とする利回りでは何年かかるか、ぜひ一度計算してみてください。
72の法則とあわせて知りたい投資の法則
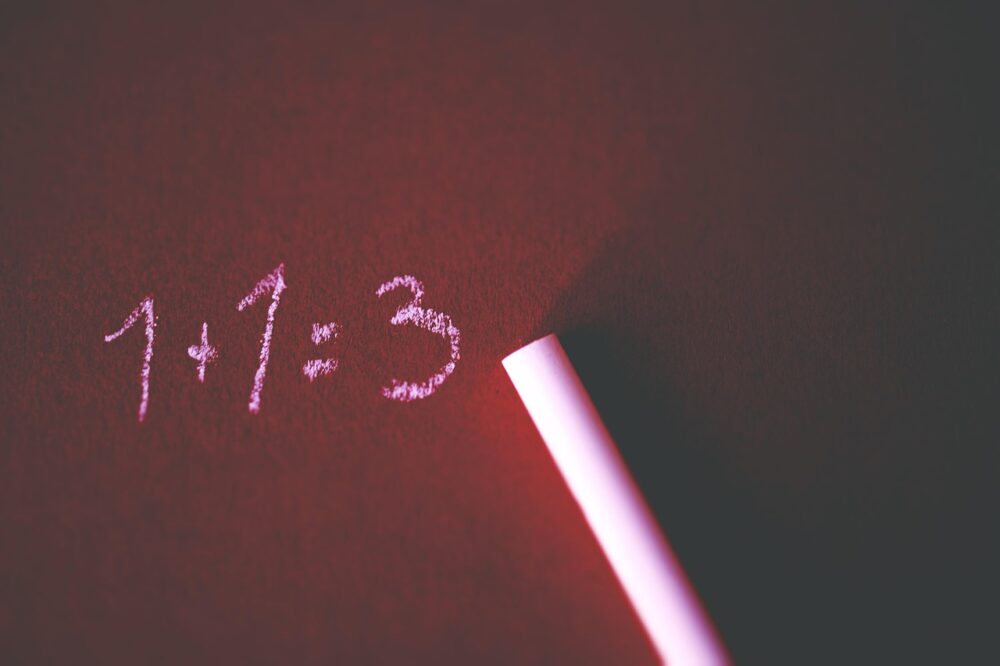
72の法則は一括投資の際に役立ちますが、ほかにも知っておくと便利な法則があります。計算式だけでなく、投資判断に影響を与える心理法則もあわせて理解することで、より盤石な資産形成プランを立てられるようになります。ここでは特に重要な4つの法則を紹介します。
積立投資で資産が2倍になる期間の目安 126の法則
毎月コツコツと積立投資をしている方におすすめなのが「126の法則」です。これは積立投資において、元本と利益の合計額が、投資した元本の総額の2倍になるまでのおおよその年数を計算できます。
126 ÷ 金利(%) ≒ 積立投資で資産が2倍になる年数
例えば、年利5%で積立投資を続けた場合、「126 ÷ 5」で25.2年となります。つまり、約25年で、積み立てた元本の総額と同じ額の利益が生まれるという計算です。72の法則は一括投資、126の法則は積立投資と覚えて、うまく使い分けましょう。
ピケティの「r>g」⇒「労働より投資が有利」について
「r > g」とは、フランスの経済学者トマ・ピケティが提唱した有名な不等式です。「r」は資本収益率(投資によるリターン)を、「g」は経済成長率(労働による所得の伸び)を指します。この式が意味するのは、「投資によって資産が増えるスピードは、労働によって給料が増えるスピードよりも速い」ということです。
これは、ただ働いて給料を貯めるだけでは、資産を持つ人との格差が広がりやすいことを示唆しています。だからこそ、労働で得た収入の一部を投資に回し、お金にも働いてもらうことが重要なのです。資産形成において、投資がいかに強力なエンジンになるかを教えてくれる法則です。
4%ルールについて
「4%ルール」は、主にリタイア後の資産活用に関する法則です。これは「年間の生活費を投資元本の4%以内に抑えることができれば、資産を減らさずに生活できる」という考え方です。例えば、7,500万円の資産があれば、その4%である300万円を毎年引き出しても、資産の成長分でカバーできるため元本が減らないとされています。
この法則から、リタイアに必要な資金額を逆算することも可能です。
年間の支出額 ÷ 4%(0.04) = 必要な資産額
このルールは、経済的自立と早期リタイアを目指す「FIRE」という生き方で重要視されており、ゴール設定の大きな目安になります。
損失回避バイアス(損失回避性)
「損失回避バイアス」とは、人は「利益を得る喜び」よりも「損失を被る苦痛」を2倍以上大きく感じてしまうという心理的な偏りのことです。このバイアスは、投資判断に大きな影響を与えます。
例えば、株価が下落した際に「損をしたくない」という気持ちから、売るべきタイミングで売れず、さらに損失を拡大させてしまうことがあります(損切りできない)。逆に、少し利益が出ると、それを失いたくない一心ですぐに売ってしまい、大きな利益を逃すこともあります。この心のクセを理解し、あらかじめ投資のルールを決めておくことが、合理的な判断につながります。
投資の法則を利用するときの注意点

これまで紹介した法則は非常に便利ですが、利用する際にはいくつか注意点があります。第一に、これらの計算結果はあくまで「目安」であるということです。投資の世界では、毎年必ず同じ利回りが保証されるわけではありません。市場は常に変動するものです。
第二に、税金や手数料が考慮されていない点です。投資で得た利益には通常、税金がかかります。また、金融商品によっては手数料も発生します。そのため、実際に手元に残る金額は、計算結果よりも少なくなることを覚えておきましょう。これらの法則は将来を約束するものではなく、計画を立てるためのツールとして賢く活用することが大切です。
投資以外にも役立つお金の法則

資産を増やすためには、投資で利益を出すことと同じくらい、支出を管理することが重要です。私たちの普段のお金の使い方は、無意識の心理的なクセに大きく影響されています。ここでは、日常の家計管理に役立つお金の法則を紹介します。これらの法則を知ることで、お金との付き合い方がもっと上手になるはずです。
収入が増えても支出が増える パーキンソンの法則
「パーキンソンの法則」とは、「支出の額は、収入の額まで膨張する」というものです。昇給して収入が増えたはずなのに、なぜか暮らしが楽にならない、という経験はありませんか。それは、収入が増えると、無意識に生活水準を上げてしまい、その分だけ支出も増やしてしまうからです。
この法則の対策として最も有効なのが「先取り貯蓄(投資)」です。給料が入ったら、まず先に貯蓄や投資に回す金額を決めて、残ったお金で生活する習慣をつけましょう。これにより、収入の増加分を自然と資産形成に充てることができます。
松竹梅の法則(おとり効果)
「松竹梅の法則」は、多くの人が3つの選択肢を提示されると、無意識に真ん中の価格帯のものを選んでしまうという心理法則です。例えば、レストランで2,000円、1,500円、1,000円のランチがあれば、多くの人が1,500円のランチを選びがちです。
これは、一番高いものは贅沢すぎ、一番安いものは品質が不安だと感じてしまう心理が働くためです。この法則を知っておけば、商品やサービスを選ぶ際に「本当に自分に必要な価値があるか」という視点で冷静に判断できます。価格の選択肢に惑わされず、自分にとって最適なものを選びましょう。
まとめ
72の法則などの投資法則は、資産形成の目標を立てる上で非常に役立つツールです。同時に、パーキンソンの法則のようなお金にまつわる心理法則を知ることも大切です。まずは「72の法則」を使い、あなたの資産がいつ2倍になるか計算してみましょう。法則を賢く使いこなし、計画的な資産形成への第一歩を踏み出してください。
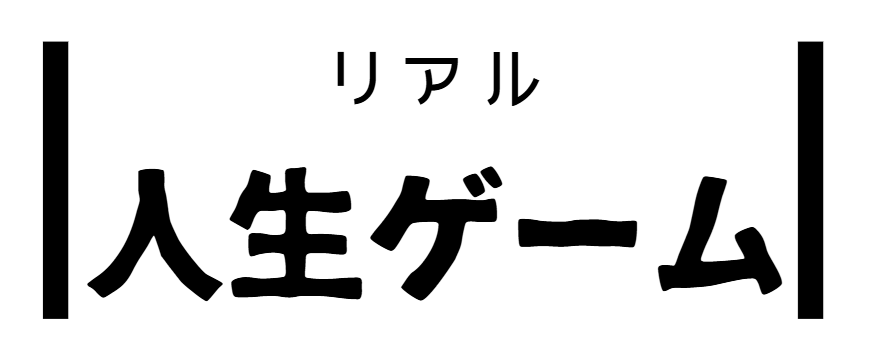


コメント