「新NISAを始めたいけど、何から手をつけていいか分からない」と悩んでいませんか?投資は難しそう、失敗したくない、という思いからなかなか一歩踏み出せない人も多いでしょう。この記事を読めば、新NISAの始め方が分かり、あなたに合った証券会社選びから口座開設、運用開始までスムーズに進められます。正しい知識を身につけ、将来の資産形成と幸福な人生への第一歩を踏み出しましょう。
第1章 新NISAの基本を理解しよう

新NISAとは?旧NISAからの変更点
2024年からスタートした新NISAは、非課税で投資ができる国の制度です。旧NISAと比べて、非課税投資枠が大幅に拡充され、より多くの金額を非課税で運用できるようになりました。生涯の非課税投資枠は1,800万円に増え、つみたて投資枠と成長投資枠の併用も可能です。
これにより、これまで以上に柔軟な資産形成が可能になり、多くの方にとって投資を始める大きなチャンスとなりました。非課税期間も無期限となり、より長期的な視点で資産を育てられる点が大きな魅力です。
新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の違い
新NISAには「つみたて投資枠」(年間120万円)と「成長投資枠」(年間240万円)があります。成長投資枠は個別株や投資信託など幅広い商品に投資でき、積極的なリターンを目指せます。
これら2つの枠は合計年間360万円まで併用可能です。
新NISAで得られるメリットとデメリット
新NISAの最大のメリットは、投資利益が非課税になる点です。通常約20%かかる税金がかからないため、効率的な資産増加が期待できます。非課税保有限度額の拡大と無期限化により、長期的な資産形成にも適しています。
一方、元本割れのリスクや、損益通算ができない点がデメリットです。旧NISAからの商品移行もできません。対策として「長期・積立・分散」投資が推奨され、特に手数料の低いS&P500や全世界株式のインデックスファンドをコツコツ積み立て、複利効果を長期で活用することが、効率的な資産形成に繋がります。
おすすめの証券口座

新NISAを始めるにあたり、どの証券会社を選ぶかは非常に重要です。ここでは、「手数料」「取り扱い商品」「得られるポイント」の3つの観点から、特におすすめの証券会社を2つご紹介します。
楽天証券
- 手数料: 新NISAでの投資信託、国内株、米国株の取引手数料はすべて0円です。
- 取り扱い商品: 投資信託の品揃えが豊富で、つみたて投資枠、成長投資枠ともに幅広い商品から選べます。
- 得られるポイント: 楽天カードを使ったクレカ積立では、積立金額に応じて最大2.0%の楽天ポイントが貯まります。また、対象銘柄の保有残高に応じてポイントがもらえるサービスもあり、貯まったポイントは投資に再利用可能です。筆者はコストパフォーマンスがよい楽天モバイルをおすすめしており、ポイント連携の観点からもイチ押しの証券会社です。
SBI証券
- 手数料: 新NISAでの投資信託、国内株、米国株の取引手数料はすべて0円です。
- 取り扱い商品: 投資信託の取り扱い銘柄数が業界トップクラスで、国内外の様々な商品から選択できます。個別株の選択肢も豊富です。
- 得られるポイント: 三井住友カードを使ったクレカ積立では、カードの種類に応じて最大4.0%のVポイントが貯まります。投資信託の保有残高に応じたポイント還元もあり、Vポイント以外にもPontaポイント、dポイント、PayPayポイント、JALマイルから選択できる柔軟性があります。三井住友カードをメインで利用している方には特におすすめです。
第2章 新NISAの始め方5ステップ

ステップ1:金融機関を選ぼう
新NISAを始める最初のステップは、金融機関を選ぶことです。前述した「手数料」「取り扱い商品」「得られるポイント」の3つのポイントを比較検討し、ご自身のライフスタイルやポイント利用状況に合った証券会社を選びましょう。特に、普段利用しているクレジットカードやポイントサービスと連携できる金融機関を選ぶと、お得に資産形成を進められます。またネット銀行を開設されていない方は併せて申請することをおすすめします。
証券会社とネット銀行の連携を活用しよう
楽天証券を選ぶ場合は楽天銀行との連携が強力です。楽天銀行の「マネーブリッジ」を設定することで、普通預金金利が優遇されます。楽天カード、楽天ポイントなど、楽天経済圏全体でポイントを活用しやすいのが特徴です。
SBI証券を選ぶ場合は住信SBIネット銀行との連携が一般的です。住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金」を利用することで、自動入出金と優遇金利のメリットを享受できます。
ステップ2:口座開設を申し込もう
金融機関を決めたら、NISA口座の開設を申し込みます。多くの証券会社では、オンラインでの申し込みが可能です。本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)とマイナンバー確認書類(マイナンバーカードや通知カードなど)が必要になるため、事前に準備しておきましょう。指示に従って必要情報を入力し、書類をアップロードすれば申し込みは完了です。
ステップ3:審査とNISA口座の開設
申し込み後、金融機関による審査が行われます。審査に通ると、NISA口座が開設されます。この手続きには数日から数週間かかる場合があるため、余裕を持って申し込みましょう。口座開設が完了すると、IDやパスワードが発行され、マイページにログインできるようになります。
ステップ4:投資する商品を選ぼう
NISA口座が開設されたら、いよいよ投資する商品を選びます。初心者には、世界中の株式に分散投資する「全世界株式型」や、米国の主要な企業に投資する「全米株式型」の投資信託がおすすめです。これらは比較的リスクが低く、長期的な視点での資産成長が期待できます。ご自身の投資目標やリスク許容度に合わせて、慎重に商品を選びましょう。
ステップ5:積立設定をして投資を開始
商品を選んだら、積立設定を行います。毎月の積立金額や積立頻度(毎日、毎月など)を設定しましょう。銀行口座からの自動引き落としや、クレジットカードでの積立が選択できます。設定が完了すれば、あとは自動で積立投資が開始され、手間なく資産形成を進められます。
第3章 新NISA実践編

余裕資金の範囲内で投資を始めましょう
投資はあくまで余剰資金で行うことが鉄則です。生活費や将来使う予定のあるお金まで投資に回してしまうと、相場が下落した際に精神的な負担が大きくなり、冷静な判断ができなくなる可能性があります。まずはご自身の生活に支障のない範囲で、無理のない金額から投資を始めましょう。少額からでも、継続することが大切です。
万が一に備え、生活防衛資金を準備しておきましょう
投資を始める前に、必ず生活防衛資金としてある程度の預貯金を確保しておきましょう。目安としては、生活費の3ヶ月から半年分と言われています。これにより、病気や失業など、もしもの事態が起きても安心して対応できます。無リスク資産があることで、投資で多少の含み損が出ても焦らず、長期的な視点で投資を続けられるようになります。
小さな利益に飛びつかず、複利の効果を活かしましょう
新NISAは長期的な資産形成を目的とした制度です。一時的に利益が出たからといってすぐに売却してしまうと、複利効果の恩恵を十分に受けられません。複利効果とは、投資で得た利益を再び投資に回すことで、利益が利益を生み出す効果のことです。これにより、資産が雪だるま式に増えていく可能性があります。短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で資産を育てていきましょう。
暴落時は買い増しのチャンスと捉えましょう
市場が大きく下落する暴落局面では、不安になって保有している商品を売却したくなるかもしれません。しかし、暴落時は「安く買えるチャンス」と捉えることができます。多くの投資家がパニックで売却する中、冷静に買い増しを行うことで、その後の回復期に大きなリターンを得られる可能性が高まります。あらかじめ決めたルールに基づいて、感情的にならずに投資を続けることが重要です。
第4章 よくある疑問を解決!新NISAに関するQ&A

新NISA口座は一人で複数開設できるか
新NISA口座は、一人につき一つの金融機関でしか開設できません。複数の金融機関でNISA口座を作ることはできないため、最初に選ぶ金融機関は慎重に検討しましょう。もし途中で金融機関を変更したい場合は、年単位で変更手続きを行うことが可能ですが、手間がかかるため注意が必要です。
新NISAで元本割れするリスクはあるか
新NISAも投資である以上、元本割れのリスクはあります。投資した商品の価格が購入時よりも下落すれば、投資元本を下回る可能性があります。しかし、長期・積立・分散投資を心がけることで、このリスクを低減できるとされています。リスクとリターンは常に表裏一体であることを理解し、ご自身の許容できる範囲で投資を行うことが大切です。
新NISAを始めるのに年齢制限はあるか
新NISAを始めることができるのは、日本国内に住む18歳以上の方です(2025年10月現在)。18歳未満の方はNISA口座を開設できません。年齢の上限はありませんので、18歳以上であれば何歳からでも新NISAを始めることが可能です。将来への備えとして、早めに始めることをおすすめします。
口座開設後、放置したらどうなるか
NISA口座を開設しても、商品を買い付けなければ特にデメリットはありません。ただし、非課税投資枠は毎年リセットされるため、利用しないと非課税で投資できる機会を逃してしまうことになります。口座を開設したら、なるべく早く投資を始めることで、非課税メリットを最大限に活用できるでしょう。
旧NISAからの移行手続きについて
旧NISAで保有している商品は、新NISAの非課税投資枠には移管できません。旧NISAの商品は、それぞれの非課税期間が終了するまで引き続き非課税で運用されます。旧NISAの非課税期間が終了した後、もし商品を売却せずに保有し続けたい場合は、課税口座に移管されることになります。新NISAはあくまで新しい制度として、別の非課税投資枠を持つことになります。
まとめ

新NISAは、非課税で効率的に資産形成ができる国の制度です。この記事では、新NISAの基本から、金融機関の選び方、口座開設の手順、そして投資における注意点までを詳しく解説しました。まずは無理のない範囲で少額からスタートし、長期・積立・分散投資を心がけましょう。
正しい知識を身につけ、今日から新NISAを始めることで、将来の不安を解消し、幸福度の高い人生へと繋がる第一歩を踏み出せるはずです。あなたの資産形成を応援しています!
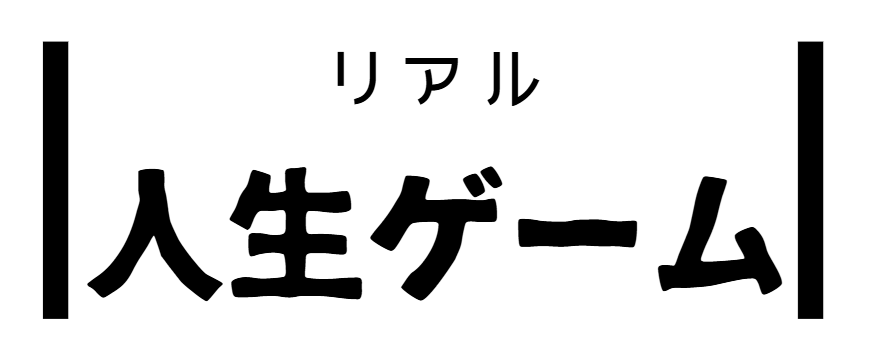


コメント